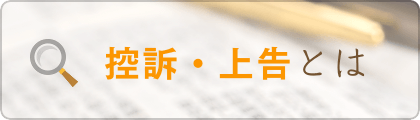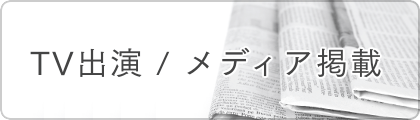余罪が原因で実刑判決を受けたときの控訴審の闘い方|控訴審での闘い方を弁護士が解説
 例えば,詐欺や横領は,反復継続して犯行が繰り返されることが多く,その被害額を全て立件してそれ相応の刑罰を与えるというのが治安維持を担う警察や検察官の姿勢です。
例えば,詐欺や横領は,反復継続して犯行が繰り返されることが多く,その被害額を全て立件してそれ相応の刑罰を与えるというのが治安維持を担う警察や検察官の姿勢です。
一方で,各犯行のすべてについて証拠が揃っているわけではなく,古い犯行については被疑者も被害者も記憶が曖昧で,証拠も散逸しているケースが多いのも事実です。
ですから,警察は事件を絞り,証拠の堅いものだけを立件し,捜査を遂げ,その余の犯行は「余罪」としてひとくくりにして,いわゆる「悪情状」として検察庁に事件送致するのが通例です。
検事も,起訴事実としては証拠が堅いものにとどめ,一部無罪を回避し,同時に,余罪を悪情状として立証して実質的に刑期に反映させようと試みます。
一審判決において,起訴された各犯行の被害額の全額ないしそれに近い金額を弁償したにもかかわらず,弁償していない余罪の存在があって示談が成立せず,結局,実刑になってしまうことがあるのです。
この場合,控訴審でどのように闘うか問題になります。もちろん,一審判決後に余罪について追加被害弁償をして示談成立を狙うという方法が確実ですが,資力がない場合に諦めるかというと,法律論で闘う道が残されています。以下のような最高裁判例があるのです。
最高裁大法廷判決昭和41年7月13日
余罪と量刑の関係について,最高裁大法廷判決昭和41年7月13日(刑集20巻6号609頁,以下「最高裁昭和41年判決」という。)は,憲法第31条(不告不理)違反,憲法第38条3項,刑事訴訟法第319条2項,3項違反(補強法則)の危険性を根拠として,「刑事裁判において,起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し,実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されない。」と判示しました。
もっとも,他方においてこの最高裁判決では,「他面,刑事裁判における量刑は,被告人の性格,経歴および犯罪の動機,目的,方法等すべての事情を考慮して,裁判所が法定刑の範囲内において,適当に決定すべきものであるから,その量刑のための一情状として,いわゆる余罪をも考慮することは,必ずしも禁ぜられるところではない。」と判示しました。
そこで問題となっている事件の原判決の判断が,前者,すなわち,余罪考慮が許容されない実質処罰類型として余罪言及にあたるのか,それとも,余罪考慮が許容される情状推知類型としての余罪言及にあたるのかがまさに問題となるわけです。
実質処罰類型と情状推知類型を区別する基準
ここで,実質処罰類型と情状推知類型を区別する基準が問題となります。上記の最高裁昭和41年判決は,1回の郵便物窃盗を公訴事実とする窃盗被告事件で,余罪たる同種事案が多数回あった事例であったところ,実質処罰類型にあたるか,情状推知類型にあたるかについて,次のように具体的に検討しています。
「原判決の判示は,余罪である窃盗の回数及びその窃取した金額を具体的に判示していないのみならず,犯罪の成立自体に関係のない窃取金員の使途について比較的詳細に判示しているなど,その他前後の判文とも併せ熟読するときは,右は本件起訴にかかる窃盗の動機,目的および被告人の性格等を推知する一情状として考慮したものであって,余罪を犯罪事実と認定し,これを処罰する趣旨で重く量刑したものではないと解するのが相当である。」
つまり,余罪の被害を重視してこれを起訴事実と同様に処罰せんとしたのではなく,あくまでも窃盗の動機,目的および被告人の性格等を,情状の一事情として判断するうえで余罪に言及したと解釈し,それは許容されるとしたのです。
この最高裁の分析手法から言えることは,実質処罰類型と情状推知類型とを区別する際の判断基準は,①余罪の金額,回数等の具体的な判示があるか否か,②余罪を犯罪事実として認定しているか,③判決文における文脈から余罪と「罪となる事実」とを混同しているか,④余罪事実から現に被告人の性格,動機,目的等の情状を推知しているかなどが重要な判断要素ないし資料となります。余罪の金額などを重視せず(上記①②③),被告人の性格や犯行動機等に重点がおかれていて,その判断の一資料として余罪を考慮している場合は,許容されるのです。もう少し裁判例を見てみましょう。
東京高判平成3年判決について
本件と類似する事案として,東京高判平成3年10月29日(判例時報1413号126頁,以下,「東京高判平成3年判決」という。)においては,他人名義のクレジットカードを利用した詐欺事案において,公訴事実は合計5回の犯行で被害総額が時価合計約29万538円であったにもかかわらず,その量刑において,余罪も含めて合計196回の被害総額963万8460円であることを認定した上で,「被告人が控訴事実に対応する金額を弁償しているけれども,被告人が本来支払うべき金額は前記の963万8460円であるから,この点は特に評価すべきものではない」などと判示した原審判断を実質処罰類型であるとして破棄しました。
その理由とするところは,原審は確かに余罪について犯行の計画性や常習性を判断する一資料とした観があり,また証拠調べにおいても余罪に関する若干の証拠が取り調べられたことからすると原審も実質処罰類型と情状推知類型を意識していたとは言えるとしつつ,結局,原審が公訴事実と余罪を一体として犯行回数,被害金額を詳細に認定し,公訴事実と余罪を含めた本件全体について量刑事情を論じ,公訴事実の内容(公訴事実の被害額を弁償したこと)は,量刑上有利な一事情として考慮するに止めたと言わざるを得ないこと,即ち,弁償事実を余罪を含めた全体の被害額からすると少ないと過小評価したこと,さらに,検察官求刑も同種事案と対比して特に軽いとは言えないこと,これらを総合して考慮すると,余罪を実質的に処罰する趣旨のもとに,被告人に対する量刑を行ったとの疑いを禁じ得ないとしたのです。
この点,安冨潔教授によれば,「証拠が十分でなく起訴できないような場合に余罪として実質上処罰しようしたのではないか」(実質処罰類型)といった観点が重要であるとしているように(「余罪と量刑―最高裁判所大法廷判決後の裁判例を中心として―」法研60巻2号230頁),検察官の訴追意思やこれを受けた裁判所の処罰意思も重要な判断基準となってきます。
仙台高判平成15年判決について
一方で,上記東京高判平成3年判決と同様,詐欺の事案で,仙台高判平成15年5月15日判決(裁判所ホームページ裁判例情報,以下「仙台高判平成15年判決」という)は,原審が「用意周到かつ巧妙に計画され,広域にわたる多数の被害者に対して,電話勧誘販売及び代金引換郵便制度を悪用し,長期間にわたり常習的に敢行された犯行の一部である」と判示したものの,余罪である詐欺の回数及びその詐取金額を具体的に認定しなかった原判決に対し,「原判決は,本件起訴以外の余罪の存在を,犯行の動機・目的,計画性,方法,反復累行性,被告人の犯罪傾向等の情状を推知する資料として用いたものであり,……本件犯行の諸情状に照らして,懲役2年6か月の原判決の不当なものではないことからしても,原判決が,余罪を犯罪事実として認定した上,これを処罰する趣旨で重く量刑したものではないことは,明らかである。」と判示しました。
要するに,この仙台高判平成15年判決と東京高判平成3年判決とを並べてみてみると,実質処罰類型か情状推知類型かの区別で重要なことは,余罪について,その回数及び金額を具体的に明示して犯罪事実として認定しているかどうかということになります。
広島高判平成14年判決について
広島高判平成14年12月10日(判例時報1826号160頁)では,原審公判期日に余罪に関する証拠が取り調べられたこと,判決文において,右余罪に関する証拠が「罪となるべき事実」を認定した証拠として「証拠の標目」に掲げられたこと,「量刑の理由」において,起訴事実以外の犯罪事実(余罪)が説示されましたことを重視して実質処罰類型と判断しました。
情状推知類型にあっても常に適法とは言えない
 例えば,スリによる窃盗事案にあって,多数回常習的にすりを行なっていたところ,最後に現行犯で逮捕され,その逮捕事実である窃盗未遂1回で起訴されたような事案があるとします。被告人の自白にかかる過去の多数回にわたる窃盗余罪は,被告人の常習性,巧妙さ,性格等の情状を推知するためにこれを取調べ,量刑の一資料とすることは,関連性と必要性があるゆえに許されるでしょう。
例えば,スリによる窃盗事案にあって,多数回常習的にすりを行なっていたところ,最後に現行犯で逮捕され,その逮捕事実である窃盗未遂1回で起訴されたような事案があるとします。被告人の自白にかかる過去の多数回にわたる窃盗余罪は,被告人の常習性,巧妙さ,性格等の情状を推知するためにこれを取調べ,量刑の一資料とすることは,関連性と必要性があるゆえに許されるでしょう。
しかし,詐欺事案,あるいは,業務上横領事案等の場合は,相当数の事件が起訴されることがあり,その場合,余罪を待たずとも常習性や巧妙さ,性格等の情状を起訴された公訴事実自体から十分推知できる場合が多いので,たとえ情状推知類型と判断されたとしても,なおも関連性ないし必要性がないとして余罪の扱いが問題とされる場合があります(「量刑実務大系2―犯情等に関する諸問題」大阪刑事実務研究会編著190頁ないし192頁)。
起訴された複数の犯行自体から十分に情状事実を評価できるのであって,それ以上に余罪を取り込んでこれに言及することは,もはや許容される情状推知類型の範囲を超えるということになります。やはり,余罪を考慮する必要性や関連性も問題となります。